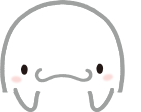塩をめぐる東方ユーラシア世界史
第2回 古代東方ユーラシアの二大勢力〜匈奴・漢の対立と塩をめぐる国家戦略
第2回 古代東方ユーラシアの二大勢力〜匈奴・漢の対立と塩をめぐる国家戦略
古代東方ユーラシアの歴史は、匈奴と漢の対立・交流関係を軸に展開した。本連載の第2回では、遊牧草原地帯で勢力を拡大した匈奴と、中国の農耕社会の発展のなかで成立した漢王朝に焦点を当て、それぞれにおいて塩がどのような役割を果たしたのかを紹介する。また、両者の係争地かつ交流の場となった地域、すなわち河套(かとう)平原とその西方の河西回廊、さらに中央アジアのオアシスへと連なる地帯の歴史的な位置づけについても併せて考えてみたい。
古代東方ユーラシア世界の見取図
まず、東方ユーラシア地域において、遊牧国家、農耕国家、オアシス都市国家群という三つの勢力が、歴史的に見てどのような関係にあったのかを確認しておこう。遊牧国家はいわゆる「草原の道」を押さえるとともに、「絹の道」上にあるオアシス都市国家群とも共生関係を築いた。遊牧民が軍事力を、オアシス民が経済力を相互に提供しあう関係である。そしてこれらの「道」を通じて鉄器などの先進的なモノや技術が西方ユーラシア世界からもたらされた。一方、中国の農耕国家にとっても「絹の道」を経てもたらされるモノや技術は貴重であった。長安など古代王朝の都城の多くが内陸部の西方に位置していたのも、当時、西側が中国のいわば玄関口であったためである。漢人たちは河西回廊よりも西のオアシス地帯を「西域(さいいき)」と呼んで関心を示し、後述するように、漢の武帝の時代に初めてこれらの地域への本格的な進出を果たした。
匈奴の勢力拡大と漢王朝との関係
匈奴は前3世紀末以降、冒頓単于(ぼくとつぜんう)のもとで強大化し、周辺の遊牧集団を糾合して東方ユーラシアの北半における一大勢力となった。そして、天山山脈の南のオアシス都市国家群も傘下に収め、「草原の道」と「絹の道」の両方を押さえることに成功した。
匈奴は、オアシスだけでなく、中国の農耕地帯にもたびたび進出した。戦国時代から秦の始皇帝の時代にかけて、黄河北方の陰山山脈に沿うように長城が築かれていたが、匈奴はこれを越えて南下し、漢初には河套平原にまで勢力を拡張した。この平原には牧畜に適した草原があり、必需品である塩も産出したから、匈奴はここを拠点にして漢王朝の中核地域を脅かすようになった。
ただ、匈奴と漢の関係は軍事対立に終始していたわけではない。両者の境域には官設の関市が置かれ、平時には交易が行われていた。遊牧民は馬や羊、農耕民は絹や茶などをそれぞれ提供しあっていたのである。おそらく塩も交易品のなかに含まれていたであろう。
漢から匈奴には人の流れもあった(その逆も然り)。王昭君(公主)や李陵(捕虜)の事例はよく知られているが、他にも例えば漢の宦官であった中行説(ちゅうこうえつ)は匈奴に送られたのち、これを単于が重用したという。匈奴の一部では農耕も行われるなど、純粋な遊牧社会というよりは、定住的要素も含むハイブリッドな社会が形成されていたと見ることができる。
中国農耕社会の発展と塩商の出現
塩は鉄とともに中国社会の発展や王朝の興亡に深い影響を与えてきた。春秋戦国時代までに西方から製鉄技術が伝わり、鉄製の農具が普及すると、農耕社会には大きな変革が起こった。華北の平原をはじめとする内陸平野部では農業開発が進行し、人口増加が顕著になったのである。また、漢代に入ると、農耕だけでなく牧畜も発達した。その結果、食塩を使用する加工保存食品がさかんに生産されるようになり、塩の需要は増加の一途を辿った。
しかし、内陸部において塩を産出する塩池や塩井などの所在は限られていたため、人口は稠密だが産塩地から遠い地域もあった。そうした地域に塩を供給する役割を果たしたのが塩商である。塩は鉄とともに中国古代社会の遠隔地商業における重要な商品となった。そして一部の塩商は莫大な利益を得て大商人へと成長していった。
古代中国における塩専売をめぐって
民生必需品である塩が利益を生むことに目をつけたのは塩商だけではなかった。中国では戦国時代にはすでに塩を国家財政の基幹資源として位置づける試みが始まった。例えば、斉の桓公(かんこう)に仕えた管仲(かんちゅう)は、塩を国家統制の対象とし、安定した財源を確保することで斉を強国に育てた。また、山西地方の解池を領有した魏は、その塩利を独占して豊かな財力を誇った。一方、秦は商鞅(しょうおう)のもとで四川盆地の塩井の開鑿をさかんに進めるとともに、解池を擁する魏を繰り返し攻撃した。最終的に戦国時代の幕を引き、中国を初めて統一したのはこの秦である。
短命に終わった秦王朝の末期の混乱のなかから、劉邦が頭角を現し、漢王朝を築いた。しかし、ちょうどそのころ北方の遊牧草原で強大化していたのが前述の匈奴・冒頓単于であった。漢は匈奴に圧迫され、河套一帯を失ったまましばらく和親政策に甘んじた。しかし、第七代の武帝の時代に入ると状況が一変した。まず、使者張騫(ちょうけん)を西域に派遣してオアシス方面諸国との連携を図り、つづいて将軍霍去病(かくきょへい)の匈奴遠征が成功し、河套平原を取り戻したのである。
この武帝の時代に、桑弘羊(そうくよう)の財政改革の一環として採用されたのが塩・鉄の専売である。物資の流通過程に国家が直接介入する均輸平準法の導入と同時に、塩や鉄の販売にも国家介入の手を広げたのである。こうした改革が行われたのは、匈奴への大規模な軍事遠征が休止した時期であった。つまり、匈奴遠征によって逼迫していた国家財政を建て直すために、商工業の統制を断行したのである。また、塩の専売を別の角度から見れば、生活必需品を通じて国家が庶民を直接的に支配する装置だったともいえる。
塩の専売はしばしば批判の的となった。その是非をめぐる論争が、桓寛(かんかん)の『塩鉄論』に記されている。官僚たちは戦費調達のために専売が不可欠と主張したが、知識人たちは民間経済を圧迫する弊害を指摘し、塩専売の廃止を訴えた。つまり、この論争は、専売を通じて国家が市場を掌握することの正当性を問うものであり、以後の中国史における国家と経済の関係をめぐる議論の先例ともなった。塩という存在が、国家権力と市場秩序をめぐる究極の対立の焦点となったのである。
漢王朝の西域経営とオアシス地帯のその後
漢王朝は、武帝から第十代の宣帝の時期にかけて、河西方面に敦煌など四郡を設置し、オアシス都市群のあるタリム盆地への進出拠点を確保した。さらに西域都護(とご)を置いて西域の経営を強化した。漢王朝は、遊牧国家匈奴とオアシス都市国家群との共生関係に、東から初めて楔(くさび)を打ち込んだのである。
その過程で、塩業の開発も進められた。漢代には塩の生産拠点を中心に「塩官」と呼ばれる官署が設置されていた。塩の専売制とも密接にかかわるこの塩官は逐次増置されていったが、全体の約半数は東方の沿海部にあった。これは海塩の生産が本格化していたことの現れといえる。一方、内陸部や辺境地帯にも塩官は設けられた。解池を含む山西や、塩井が盛んに掘られていた四川のほか、匈奴との係争地であった河套平原から甘粛方面にかけても塩官の設置が進められた。つまり、塩の統制は、漢王朝の支配領域の拡大や統治の安定と密接に関連していたともいえる。
後漢の時代に入ってからも、西域都護の班超(はんちょう)の活躍により、オアシス地帯は中国農耕国家の影響下に置かれた。しかしその後、漢王朝は西域経営を維持できなくなり、代わって北西インドのクシャーナ朝の影響が増すようになった。それとともにインド商人や中央アジアのバクトリア商人、そしてソグド商人がオアシス都市国家群へと活動範囲を広げ、東方ユーラシア世界にも積極的に進出するようになった。インド由来の仏教が中国に伝わって来たのもこのころである。
以上のように、古代東方ユーラシアの歴史は、遊牧国家匈奴と農耕国家漢王朝の対立・交流を軸に展開し、さらにオアシス都市国家群も重要な位置づけにあった。塩は遊牧民にとって欠かせない資源であったが、むしろ中国における農耕社会の発展や国家形成の過程できわめて重要な役割を果たしたといえる。とくに塩を国家の財政基盤として位置づける専売制の導入は、歴代王朝の政策の基調の一つとなったのである。
矢澤知行(近畿大学国際学部教授)
主要参考文献
影山剛『中国古代の商工業と専売制』東京大学出版会、1984年.
宮崎市定「歴史と塩」『アジア史研究』2、同朋舎、1985年.
佐伯富『中国塩政史の研究』法律文化社、1987年.
尾形勇・平㔟隆男『中華文明の誕生』(世界の歴史2)中央公論社、1998年.
佐原康夫「中国古代の貨幣経済と社会」『岩波講座世界歴史』3、岩波書店、1998年.
林俊雄「草原遊牧文明論」『岩波講座世界歴史』3、岩波書店、1998年.
荒川正晴「漢晋期の中央アジアと中華世界」『岩波講座世界歴史』5、岩波書店、2021年.