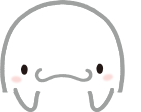塩をめぐる東方ユーラシア世界史
第3回 “東方ユーラシア王朝”唐における塩政の展開
第3回 “東方ユーラシア王朝”唐における塩政の展開
唐(618–907年)は、長期にわたり広大な領域を支配したという点で、中国の歴史を代表する王朝とみなされがちである。しかし実際には、王朝を通じて政争や内乱が絶えず、不安定で流動的な側面を抱えていた。さらにいえば、複雑なルーツと多元的な性格を有することから、中華王朝という枠には収まりきらない“東方ユーラシア王朝”と呼ぶのがふさわしい。本連載の第3回では、唐王朝の成立までの歴史を概観したうえで、唐代における塩政の展開過程をたどる。とくに安史の乱後に起こった画期的な変化に注目し、塩をめぐる動乱から唐滅亡に至る経緯を確認する。最後に、一連の歴史の意義を東方ユーラシア史の視点から考察してみたい。
“拓跋国家”の系譜と唐王朝の成立
4世紀以降、遊牧民の活動はユーラシア大陸各地で大きな影響を及ぼした。例えば、西方では遊牧民フン人の西進がゲルマン人の大移動を引き起こしたとされる。そして、今回取り上げる唐王朝も、その系譜をさかのぼると、いわゆる“拓跋(たくばつ)国家”の出発点にあたる北魏に行き着く。
386年、遊牧民・鮮卑(せんぴ)の拓跋珪(たくばつけい、道武帝)が北魏を立て、第3代太武帝のもとで華北が統一された。北魏はもともと遊牧社会を基盤とする国家であったが、華北の農耕地帯を統治するために均田制を導入した。その後、北魏は東西に分裂するが、”拓跋国家”の系譜は北斉・北周を経て隋王朝へと受け継がれる。その間に、租庸調制や府兵制など、のちに唐へと継承される諸制度が創始された。これらはいずれも華北の農民たちを組織化し、その労働力や兵力を国家が統制する仕組みであった。
そして618 年、隋に代わって唐が成立する。唐を建てた李氏一族が武川鎮(ぶせんちん)軍閥の出身であったことは注目に値する。この軍閥は鮮卑に起源をもち、その後も支配層であり続けた貴族集団である。拓跋氏に代表される遊牧的支配層は、華北の漢人有力者と融合しながら、唐に至るまで国家形成の主導権を握り続けたのである。こうして成立した唐王朝は、遊牧国家の伝統を継承しつつ、中華的秩序の確立を目指し、さらには西域にも勢力を伸ばした。その多元的性格ゆえ、唐はまさに “東方ユーラシア王朝”と呼ぶにふさわしい。
唐代初期の塩政と安史の乱の影響
建国当初の唐は、均田制と租庸調制を基盤とする隋代までの財政システムを引き継いだ。塩政についても、塩の生産に従事する民戸(塩戸)に軽い税を課すにとどまり、塩の流通や販売を担う地方豪族や商人に対しては緩やかな統制しか行わなかった。当時は国家の財政規模がそれほど大きくなく、既存の財政システムが機能していたため、塩の専売収入に依存する必要はなかったのである。
しかし690年、則天武后(そくてんぶこう)が即位して周王朝(武周)を立て、唐は一時断絶する。その後、唐王朝は復活したが、政争は止まず、第9代玄宗のもとでようやく安定期を迎えたかに見えた。ところが755年、唐の統治体制を根底から揺るがすことになる安史の乱(安禄山・史思明の反乱)が勃発する。
戦乱によって流民が激増し、均田制と租庸調制は機能不全に陥った。戸籍を基盤とする従来の税制では国家財政を維持することができなくなったうえ、乱の鎮圧過程で藩鎮と呼ばれる地方の諸勢力が独立傾向を強め、中央への納税を拒む者も出てきたため、国家の財政基盤は著しく縮小した。この危機のなかで唐王朝は新たな財源の確保を迫られた。
そこで第10代の肅宗(しゅくそう)のもと、第五琦(だいごき)が塩鉄使(塩の専売を司る財務官)となり、緊急の財政再建策として塩専売制が開始された。塩の生産から流通・販売まで官営を原則とするこの制度は、財政収入の増加をもたらしたが、膨大な管理・流通コストがかかった。また、安史の乱の終結後も地方の藩鎮の強大化は止まず、塩の専売権や流通経路は往々にして彼らに握られ、専売制は行き詰まるかに見えた。
劉晏の塩法改革と新たな財政システムの構築
こうした行き詰まりを打開したのが、第11代の代宗(だいそう)に仕えた劉晏(りゅうあん)である。8世紀後半、彼は画期的な塩政改革を実施した。新制度の骨子は次の通りである。
まず、塩の生産は各地の民間の塩戸に委ね、国家がそれを買い上げたうえで、国家の定めた価格で特許商人に払い下げた。商人たちは塩を各地に輸送して販売し、国家は商人たちから塩税を定点徴収した。
この制度の革新性は次の二点にある。第一に、国家が市場の媒介者に徹した点である。官僚機構を肥大化させることなく、商人のネットワークと市場のメカニズムを活用して低コストで塩を流通させ、安定的に商税を確保した。第二に、迅速な情報伝達システムを整備した点が挙げられる。塩の主産地や、販売要地となる全国の主要都市に巡院と呼ばれる出先機関を設置し、塩の違法な取引の取り締まりを行ったほか、物価や市場動向を逐一報告させた。これにより、合理的な塩の需給調整が可能となり、塩価の安定が図られた。
劉晏の改革を経て、塩利収入は唐王朝の歳入の半分以上を占めるまでに成長した。この収入は中央政府の直轄財源として運用され、地方の藩鎮に対抗する基盤となった。また、塩利収入は大運河を利用した漕運(官営の物資輸送)の経費にも充当され、首都圏への糧米供給体制の再建にも寄与した。
この新たな財政システムは、農業中心財政から商業中心財政へ、直接税から間接税への転換を意味しており、その後の宋・元・明・清にも継承される効率的・集約的運営方式の原型となった。
塩をめぐる動乱と唐王朝の滅亡
劉晏によって再構築された塩専売制は、唐後期の財政を支える重要な柱となったが、一方で新たな社会問題も引き起こした。とくに深刻だったのは、塩の密売である。塩の専売価格と密売価格の差が拡大するにつれ、貧しい民衆は正規の価格で塩を購入できなくなった。その需要と供給の隙間を埋めたのが塩の密売商人、すなわち塩徒である。彼らは次第に組織化・武装化し、その中から王仙芝(おうせんし)や黄巣(こうそう)が現れた。
875年、黄巣は王仙芝の反乱に呼応して蜂起し、その後を継いで大規模な反乱を展開した。黄巣の軍勢は、塩の密売ネットワークを活用して各地を転戦し、既存の流通ルートを掌握して補給を確保した。ついには長安を占領して斉王朝の樹立を宣言したが、ほどなくして李克用(りこくよう)を中心とする藩鎮勢力に包囲され、約10年に及ぶ反乱は鎮圧された。しかし、この時点ですでに各地の藩鎮が互いに争う段階に入っており、唐王朝の滅亡はもはや避けられなくなっていたのである。
ここまで見てきたように、唐代における塩政の展開は、東方ユーラシア世界における「遊牧と農耕」「国家と市場」「中央と地方」のせめぎ合いを象徴するものであった。唐王朝は遊牧的統治システムと中華的統治システムの融合として成立したが、初期から不安定な要因を抱えていた。その後、安史の乱という危機を経て、塩専売に市場メカニズムを組み込んだ新たな財政システムが生み出された。これと並行して均田制に象徴される中央集権的かつ農業中心の体制は崩れ去り、代わって藩鎮など地方の勢力が割拠するようになったのである。以上に述べたような大転換を経て、東方ユーラシア世界は次の時代に向けた新たな歴史的展開を見せていくこととなる。
矢澤知行(近畿大学国際学部教授)
主要参考文献
陳寅恪『唐代政治史述論稿』商務印書館、1943年.
佐伯富『中国塩政史の研究』法律文化社、1987年.
宮崎市定『大唐帝国 中国の中世』中公文庫、1988年.
礪波護・武田幸男『隋唐帝国と古代朝鮮』〈世界の歴史06〉中央公論社、1997年.
杉山正明『遊牧民から見た世界史:民族も国境もこえて』日本経済新聞社、1997年.
氣賀澤保規『絢爛たる世界帝国:隋唐時代』〈中国の歴史06〉講談社、2005年.
森安孝夫『シルクロードと唐帝国』〈興亡の世界史05〉講談社、2007年.
辻正博「隋唐国制の特質」『岩波講座世界歴史』6、岩波書店、2022年.
丸橋充拓「唐後半期の政治・経済」『岩波講座世界歴史』7、岩波書店、2022年.