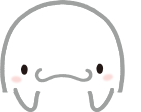くらしお古今東西
神奈川県
神奈川県と塩
東京湾岸の大師河原等では、江戸時代から明治末まで、入浜式塩田による塩づくりが行われていました。
塩のsenjutsu
第5回 塩の効能とsenjutsu(戦術)
第4回までは、戦国大名のsenjutsu(戦術)における塩の確保を軸に、生産から流通に至る民衆や商人、領主の動きを見てきました。第5回では塩の利用方法を見ることで、戦国大名のsenjutsu(戦術)の一端にふれていきたいと思います。
戦国大名関係の史料で見られる塩関係の流通品の中に「塩あい物」があります。天文13年(1544)12月、北条氏は鎌倉荏柄天神社の造営費を集めるために設置された関所に係る規定を定めますが、商人からは麻・紙・布類の荷物は10文、あい物馬は5文を徴収するとしています(『戦北』6-4630)。藤沢(神奈川県藤沢市)の大鋸引(おがひき)頭として知られる森木工助は、永禄4年(1561)閏3月に新規に商売を始め、北条氏に願い出て塩あい物役は2年間、酒役は永く免除することを保障されています(『同』1-694)。同7年(1564)9月、北条氏は鎌倉街道の多摩川の渡し場であった関戸郷(東京都多摩市)に対し、前々からの市日を定め、同9年からの平時と戦時の伝馬負担を規定し、濁酒役と塩あい物役を免除しています(『同』1-864)。役銭の賦課や免除の実態から、さまざまな流通品の中で塩あい物の占める大きさをうかがうことができます。
あい物(相物)とは一般に干魚、塩魚を意味し、乾燥させたり塩漬けにしたりすることで旨味を増す効果もありますが、何より保存性を高める目的があったと考えられます。永禄3年(1560)2月、北条氏は小田原城に近い国府津(神奈川県小田原市)の船主村井宗右衛門に対し、城に毎月納める魚の種類と額について細かく定めていますが、その中で「魚が傷むので塩をして上納しなさい、ただし随時無塩で上納するのは船主の随意である」とし、特に鯛については「塩にても無塩にても随意である」としています(『神』3-7136)。
そこで、魚を運ぶ際の塩の使用の有無を見てみましょう。天正12年(1584)1月5日に玉縄城(神奈川県鎌倉市)城主北条氏繁の後室(未亡人)が、翌6日までに鯛30枚と鮑100盃を夜通しかけてでも運ぶよう命じ、魚類は無塩と指定しています(『戦北』4-2613)。この史料は横須賀市指定文化財となっており、玉縄城近隣の三浦郡の漁村に魚の調達を命じたもののようですが(横須賀市HPによる)、時期的に見て正月の料理に使われ、近場ということもあり新鮮さが求められたのでしょうか。一方、北条氏忠が急用として鰹を運ばせた際には、うす塩をして夜通し運ぶよう命じています(『神』3-9488)。塩の使用の有無には魚の種類や日持ち、さらには受け手側の用途や調理法なども関係していたかもしれません。
一方、戦場に運ばれる魚には保存性とも関わって、塩が使用されていたようです。天正12年10月、北条氏直は江ノ島下之宮別当から塩漬けの鮑を贈られ、鮑は縁起物ということで、戦陣での勝機に乗ったことを喜んでいます(『戦北』4-2719)。同13年(1585)8月、北条氏政は須賀(神奈川県平塚市)に対し、出陣先(『同』4-2827では、7月には岩付[埼玉県さいたま市]方面に兵を向けています)への御用として大ぶりの鯛20枚を翌日の晩までに届けるよう命じ、鯛は引きあげた浜でうす塩をしてから船で運ばせています(『同』4-2847)。新鮮なうちに塩をすることで、軍事物資として保存に耐える効果が期待されたのでしょう。
塩の保存効果という点でいうと、戦場では戦功として挙げた首や鼻の保存にも塩が使われたと予想されますが、戦国大名関連の史料にはなかなか出てきません。そこで一つ、戦場での塩の用途として、傷の治療に使われた可能性を考えてみたいと思います。
江戸時代初期に成立したとみられる『藤葉栄衰記』(『続群書類従』22上)は、陸奥国須賀川(福島県須賀川市)の二階堂氏の中世の歴史を叙述した軍記物ですが、その中に「鏑木藤十郎喧嘩之事」という話が載っています。鏑木は関東小田(茨城県つくば市)の牢人で石川郡辺田(場所は不明)に落ちのび、城主弾正(百目木城[福島県二本松市]城主石川光昌のことか)の許にいました。あるとき所用で須賀川に出かけたところ、出会った知人に接待をしたいからと酒屋に誘われました。ところが、その酒席で酔客たちと口論となり、大力の持ち主であった鏑木は喧嘩相手たちを打ち伏せますが、帰り道に襲撃されて深手を負います。ようやく帰宅すると、見舞いに来た人が、傷に塩を塗れば痛くもなく早く治ると言います。鏑木は想像以上の激痛になると思い、内心は嫌々ながらも、たくさんの塩を取り寄せて見舞い客に塗ってくれと頼みました。見舞客は他人の痛みも顧みず急所ごとに塩を塗るので、鏑木は激痛に襲われますが、痛くないふりをしてやり過ごしたところ、傷は治ってきました。それでもまだ痛みが残るので、今度は切り口から膿を出し、薬草を煎じて貼ったところ全快しました。その後は会津や須賀川で武功を挙げたといいます。
想像するだけでも痛くなってしまう話ですが、塩には殺菌効果があったのでしょう。『雑兵物語』に載っている奇妙な民間療法の話よりも現実味がありそうで、実際の戦場でも兵士の傷の治療に塩が使われた可能性があるのではないかと想像してみたくなります。
阿部浩一(福島大学行政政策学類教授)
【参考】
横須賀市指定重要有形文化財 北条氏繁後室朱印状(2024年1月29日閲覧)
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8120/bunkazai/shi31.html
注)略記した出典は以下の通りです。数字は巻-史料番号ないし掲載ページです。参考になさってください。
『戦北』=『戦国遺文後北条氏編』1~6、『神』=『神奈川県史』資料編3古代中世3下
これまでの連載はこちら
第1回 戦国大名のsenjutsu(戦術)と塩の関わり(滋賀県のページ)
第2回 塩の生産と確保のsenjutsu(戦術)(静岡県のページ)
第3回 塩の流通・商人とsenjutsu(戦術)(山梨県のページ)
第4回 senjutsu(戦術)としての塩留(埼玉県のページ)
続きはこちら
最終回 戦国を生き抜いた武将たちと塩づくりのsenjutsu(戦術)(千葉県のページ)
塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会事務局より
今回の記事については、対象が神奈川県、埼玉県、福島県にまたがりますが、主な記述対象である神奈川県のページに掲載しています。
塩にまつわる習俗
夜間の運搬を忌む
塩は夜間に運ぶものではなかった。塩を夜間に運ぶのを嫌がる話は全国各地に残されている。津久井郡内郷村(現相模原市)でも、塩を夜運ぶのを嫌ったといわれている。何故かというと、オオカミが塩を好むからだという。
しかし、どうしても夜間に塩を運ばなければならない時には、硫黄がついた付木を持つようにしたという。
落合 功(青山学院大学経済学部教授)
参考文献:『塩俗問答集 常民文化叢書<3>』渋沢敬三編
塩にまつわる人物
佐々木久左衛門
幕臣。寛文11(1671)年、原町田村(現東京都町田市)の豪農・武藤喜左衛門を説いて大師河原(現川崎市)に塩田をつくらせました。ただし、その塩は赤色で質が悪い「抱塩(たきしお)」と呼ばれるものでした。他の地方の「抱塩」は江戸で販売することが認められていませんでしたが、幕臣である久左衛門の画策によるものでしょうか、安政年間(1855-1860)まで、大師河原の「抱塩」だけは江戸市中で販売することが認められていました。
参考文献:『大日本塩業全書 第三編』