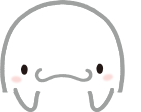くらしお古今東西
岡山県
岡山県と塩
江戸時代以降、味野地方などに大規模な入浜式塩田が築かれ、盛んに塩作りが行われました。その後昭和40年代まで、岡山県は塩田による塩づくりの中心地の一つでした。
瀬戸内塩業人物伝
第1回 野﨑武左衛門(のざき ぶざえもん)
野﨑武左衛門は寛政元(1789)年味野村(現倉敷市児島味野)で誕生しました。武左衛門が誕生した頃、野﨑家は没落状態でした。当時の児島地方は児島三白(塩・綿・いかなご)と呼ばれる特産品があり、特に綿については瑜伽山への参詣の土産物としての真田紐や小倉帯のほか、各種織物業が盛んで、たくさんの足袋製造業者がいました。野﨑家も家の再興を企図して、足袋の製造販売に着手することになったのです。足袋の製造が軌道に乗ると、瀬戸内海沿岸を中心に周防・長門(いずれも現山口県)あたりまで販路を拡張するようになりました。足袋の販売で得た利益は120貫目におよんでいましたが、足袋の製造販売に限界を感じていた武左衛門は児島郡天城村(現倉敷市藤戸町天城)で大庄屋格を勤めた中島富次郎(後妻まちの伯父)に助言を求めた結果、塩田地主の道を歩むことになりました。
武左衛門の塩田開発
武左衛門はまず味野と赤崎の沖の浅海に塩浜を築造しました。文政11(1828)年には味野村沖新開の汐止(塩浜と外海を隔てる堤防)が完成、翌文政12(1829)年には赤崎村(現倉敷市児島赤崎)沖新開の汐止が完成しました。その際、味野村と赤崎村の両村からそれぞれ一字ずつをとって「野崎浜」と名づけ、武左衛門自身も「昆陽野(こやの)」という姓から「野崎(野﨑)」へと改姓しました。
その後も次々と塩田開発を行っていきます。天保2(1831)年には日比村(現玉野市日比)に日比亀浜が、同12(1841)年には山田村(現玉野市山田)に東野﨑浜(南浜)が、嘉永6(1853)年には邑久郡久々井村(現岡山市東区久々井)に久々井浜が完成しました。この頃武左衛門は家を嫡子常太郎に譲ってしばらくは悠々自適の生活を送っていましたが、安政2(1855)年当主の常太郎が35歳という若さで死去し、武左衛門は再び塩田経営に関与することになります。その後文久3(1863)年には東野﨑浜(南浜)の北に隣接して東野﨑浜(北浜)が完成しました。東野﨑浜が築かれて以降はこれと区別するため野﨑浜は「元野﨑浜」とも呼ばれるようになりました。
武左衛門の遺訓
武左衛門は死去直前の元治元(1864)年に7か条の遺訓をのこしています。以下に一部紹介したいと思います。
- 身代(しんだい)は一種の産のみ託(よ)せおくべからず。
吾家の如きは塩田・田地・永納(えいのう)の三種に分つべし。かく分ち置くときは天災・凶作・変乱等にあふとも、三種の中孰れか安穏に保つことを得べき理なり。平常の生計は身代の三分一と心得たらんには危きことなかるべし - 新なる事業を企て財利を得んとする計画はなすべからず。たゞ固有の身代を減らさじと心懸くれば自然増殖するものぞ
- 無益と思ふわざには、つとめて金銭を費やさゞるやう心懸くべし、公共の利益あることにはいさゝかも吝(おし)むべからず(中略)
右の条々は子々孫々に伝へて常に大切に之を守り、家名を墜さゞるやう心懸くべきもの也
遺しおく教まもらば生(うみ)の子の
ちよに八千代に家は栄えん
元治元年甲子八月
野崎武左衛門源弣(みなもとのゆづか)
武左衛門は野﨑家の家業を塩田・田地・永納の三種のみに限定しました。ここでいう「永納」とは、藩への貸付けではないかと故太田健一山陽学園大学名誉教授は推測しています。また、新たな事業は行おうとしないことと明言し、しかしながら公共の利益への投資は惜しまないようにと言い残しています。
その後の野﨑家
武左衛門が元治元年8月29日に死去した後、家督は孫の武吉郎(ぶきちろう)が継ぐこととなりました。武吉郎は明治23(1890)年には貴族院議員となり、実業活動のほか、社会事業や教育事業、衛生面での支援、罹災者への援助等にも積極的に対応しました。
また、祖父武左衛門の遺訓を守り、明治20(1887)年に制定された家則についても、武左衛門の遺訓を拡大解釈する形で、家業の根幹を塩田・耕宅地・貸付金・諸公債証書・貸家の5つに定めました。上記の「永納」はここでは「諸公債証書」となっており、また明治29(1896)年には「国債」に絞っています。
このように、武左衛門の遺訓を守っていく形で子孫は塩業経営を行ってきました。現当主である野﨑泰彦氏はナイカイ(野﨑家は現在ナイカイ塩業株式会社という会社形態をとっています)のアイデンティティーは「塩屋であるということ」と発言されています(2008年7月19日 山陽学園大学公開講座)。このことからも、塩生産を第一に経営を行っていることが確認できます。
小柳智裕(就実大学経営学部准教授)
参考文献
多和和彦『児島産業史の研究』「児島の歴史」刊行会、1959年
ナイカイ塩業株式会社社史編纂委員会編『備前児島野﨑家の研究』山陽新聞社、1987年
続きはこちら
第2回 久米栄左衛門(くめ えいざえもん)(香川県のページ)
第3回 吉井半三郎(よしい はんざぶろう)(広島県のページ)
塩づくりの歴史
岡山県における弥生時代~平安時代の製塩
岡山県は南部に平野があり、海岸には多数の砂浜が展開し、沖には大小様々な島々が点在している。また、典型的な瀬戸内海式気候で温暖少雨であり、塩づくりには最適の環境であった。
岡山県における最初の塩づくりは、塩分濃度を高めた海水を小形土器(製塩土器)で煮沸・煎熬(せんごう)する「土器製塩」による。土器製塩は弥生時代中期後半に始まる。製塩土器はワイングラス形に脚台部が付いたもので、土器の外面をヘラで削って、器壁を薄くする独特の技法が用いられた。西日本では最も古い時期の土器製塩であり、岡山県児島・香川県小豆島(古くは吉備)・兵庫県家島諸島を中心に開始された。出現理由については三つの説があり、第一に児島地域自生説、第二に東北地方の縄文時代晩期における土器製塩の影響説、第三に朝鮮からの影響説である。弥生時代後期になると、岡山県南部の海岸部、特に南部平野の海岸部で盛んに土器製塩が行われた。
古墳時代前期には、製塩土器は前時期と同じくワイングラス形に脚台部が付く形態であるが、土器を薄く作る技法が土器外面を叩きしめる技法に変化している。土器製塩遺跡は平野(農耕地)の無い海岸部や島嶼部に多数展開している。
古墳時代中期になると製塩土器の形状が変化し、小形のコップ形で脚台部は無くなる。土器製塩遺跡は前時期と同じく農業生産のできない海岸部や島嶼部に存在している。
古墳時代後期になると製塩土器は丸底甕形に変化し、大形化する。また、遺跡数が増加し、大規模な遺跡が多数出現する。香川県香川郡直島町(古くは吉備)喜兵衛島製塩遺跡は、石敷製塩炉が複数存在し、極めて莫大な量の製塩土器が廃棄されており、大量の塩を生産していた。「欽明十七<556>年の児島屯倉の設置」に見られるように、生産した塩のほとんどは、当時の倭王権の所在した奈良県を始めとする近畿地方に運ばれていたのであろう。
飛鳥・奈良時代になると、製塩土器は深鉢形で尖り底の形態になり、遺跡数が減少傾向になってくる。また、「霊亀二<716>年、備中国浅口郡の飛鳥寺焼塩戸」などから、土器製塩以外の技法(浜での砂採鹹(さいかん))による塩生産が行われていたと考えられる。さらに、深鉢形の堅塩土器が出現し、堅塩(きたし)が生産されていた。堅塩土器で、製塩土器(煮沸・煎熬土器)や塩浜技法でつくった粗塩に熱を加えて焼き、固形塩(堅塩)をつくった。岡山県(備前国・備中国)の塩は、奈良時代の律令政府への貢納品として、平城京(奈良県奈良市ほか)に搬入されている。塩は籠に入れ、そこに荷札木簡(一例として、「・備前国児嶋郡三家郷・/牛守部小成/山守部小廣∥二人調塩二斗」)を付けて運ばれた。負担した「調塩」の塩の生産方法がすべて「土器製塩」であったとするには疑問があり、一部は「塩浜での砂採鹹による塩生産」であったかもしれない。
平安時代になると土器製塩は著しく衰退する。堅塩土器による堅塩生産は継続された。また、塩浜が多数展開するようになると考えられる。「延喜式」によれば、平安時代も備前国に「調塩」・「庸塩」、備中国に「調塩」が課せられていた。
このように、岡山県は最も初期に塩生産を開始し、古墳時代後期には最大規模の塩生産を行った、有数の塩生産地であった。生産した塩の大半は、近畿地方に搬出していた。
岩本正二(日本塩業研究会会員)